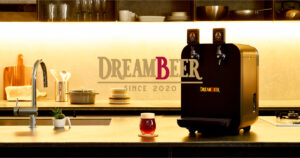クラフトビールが日本で注目され始めてから、もう10年以上が経ちました。一時期は街のあちこちにクラフトビール専門店が誕生し、大手コンビニでも地ビールコーナーが設けられるほどでした。しかし最近では「クラフトビールブームは終わったのでは?」という声も聞こえてきます。実際のところ、クラフトビールの人気はどうなっているのでしょうか。市場の動向や消費者の嗜好の変化、そして専門家の見解から、クラフトビールの現在地と未来を探ってみましょう。
クラフトビールの現状を探る
クラフトビールは2010年代半ばから日本でブームとなり、多くの醸造所が誕生しました。しかし、ここ数年でその熱は少し落ち着いてきたようにも見えます。実際の数字や市場の動きから、現在の状況を確認してみましょう。
数字で見るクラフトビール市場の変化
日本のクラフトビール市場は、2015年頃から急速に拡大し始めました。国税庁のデータによると、地ビール醸造所(いわゆるマイクロブルワリー)の数は2015年に約200か所だったものが、2022年には約450か所まで増加しています。市場規模も拡大し、2022年には約400億円規模に達したとされています。
しかし、成長率に目を向けると変化が見えてきます。2015年から2019年までは年間20%以上の成長を記録していましたが、2020年以降は成長率が一桁台に落ち着いてきました。これは市場が成熟期に入ったことを示しているのかもしれません。
| 年 | 醸造所数 | 市場規模 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 約200か所 | 約150億円 | 25% |
| 2019年 | 約380か所 | 約350億円 | 22% |
| 2022年 | 約450か所 | 約400億円 | 8% |
「ブーム終焉説」が囁かれる理由
クラフトビールのブームが終わったと言われる背景には、いくつかの要因があります。
まず、新型コロナウイルスの影響は無視できません。飲食店の営業制限やイベントの中止により、クラフトビールを提供する場が減少しました。クラフトビールは「体験」や「場」と結びついていた部分が大きく、その機会が失われたことで熱が冷めた面があります。
また、クラフトビールの価格帯の高さも課題です。一般的なビールに比べて1.5倍から3倍ほどの価格設定が多く、インフレや物価上昇の中で「贅沢品」として敬遠される傾向も見られます。
さらに、新しい酒類カテゴリーの台頭も影響しています。ハードセルツァーや低アルコール飲料、ノンアルコールドリンクなど、多様な選択肢が増えたことで、クラフトビールへの注目度が相対的に下がっているのです。
大手ビールメーカーの動向
クラフトビールブームを受けて、キリン、アサヒ、サッポロ、サントリーといった大手ビールメーカーも市場に参入しました。彼らの動きからも、クラフトビール市場の行方を読み解くことができます。
クラフトビールへの参入状況
大手メーカーのクラフトビール市場への参入は、主に二つの方法で行われてきました。一つは自社でクラフトビールブランドを立ち上げること、もう一つは既存のクラフトブルワリーを買収することです。
キリンビールは「スプリングバレー」ブランドを展開し、専門店も出店しています。また、ヤッホーブルーイング(「よなよなエール」で知られる)との資本提携も行いました。アサヒビールは「クラフトマンシップ」シリーズを展開し、サッポロビールは「SORACHI1984」などのクラフト志向の商品を販売しています。
興味深いのは、大手メーカーの参入が必ずしもクラフトビール市場を縮小させていないことです。むしろ、彼らの参入によって認知度が上がり、市場全体が拡大した側面もあります。
従来商品とのすみ分け戦略
大手メーカーは従来のビール商品とクラフトビールを明確に区別して販売しています。価格帯、販売チャネル、ターゲット層を変えることで、カニバリゼーション(自社製品同士の共食い)を避ける戦略です。
例えば、従来のビールは大量生産・大量販売のモデルで、スーパーやコンビニを主な販路としています。一方、クラフトビールは少量生産で高付加価値を訴求し、専門店や直営店、オンラインショップなどを通じて販売する傾向があります。
| 商品カテゴリー | 価格帯 | 主な販売チャネル | ターゲット層 |
|---|---|---|---|
| 従来のビール | 200〜300円 | スーパー、コンビニ | 幅広い年齢層 |
| クラフトビール | 400〜800円 | 専門店、直営店、EC | 20〜40代、こだわり層 |
この戦略により、大手メーカーは両市場で存在感を示しながら、クラフトビール文化の普及にも一役買っています。
消費者の嗜好変化を読み解く
クラフトビールの現状を理解するためには、消費者の嗜好がどのように変化しているかを知ることが重要です。お酒の楽しみ方や価値観の変化が、クラフトビール市場にも大きな影響を与えています。
お酒の多様化と選択肢の広がり
ここ数年で、お酒の選択肢は格段に広がりました。クラフトビールだけでなく、クラフトジン、クラフトウイスキー、日本ワインなど、「クラフト」や「地域性」を謳った商品が増加しています。また、健康志向の高まりから、低アルコール飲料やノンアルコール飲料も人気を集めています。
特に若い世代を中心に「飲み方の多様化」が進んでいます。一晩中同じお酒を飲み続けるのではなく、様々な種類のお酒を少量ずつ楽しむ「ハシゴ飲み」や「飲み比べ」のスタイルが定着しつつあります。
このような環境では、クラフトビールは「選択肢の一つ」という位置づけになりつつあります。かつてのような「特別なもの」から「日常的な選択肢の一つ」へと変化しているのです。
「こだわり消費」の行方
クラフトビールブームの背景には、「こだわり消費」の流れがありました。大量生産品より少し高くても、こだわりや物語のある商品を選ぶ消費行動です。この傾向は今も続いていますが、その対象が多様化しています。
例えば、食品分野では「クラフトチョコレート」「クラフトコーヒー」など、様々な「クラフト」製品が登場しています。また、サステナビリティや地域貢献といった価値観も、消費選択の重要な要素になっています。
クラフトビールもこの流れに対応し、単に「珍しい味」を提供するだけでなく、地域の特産品を使用したり、環境に配慮した製法を採用したりするブルワリーが増えています。消費者の「こだわり」の中身が変化する中、クラフトビールも進化を続けているのです。
専門店オーナーに聞いた本音
クラフトビールの現場では、どのような変化が起きているのでしょうか。専門店オーナーたちの声から、市場の実態を探ってみましょう。
売上の推移と客層の変化
東京都内でクラフトビール専門店を経営する山田さん(仮名)によれば、2018年頃がピークで、その後はやや落ち着いた状態が続いているとのこと。「以前は珍しさで来店するお客様も多かったですが、今は本当にビールが好きな方が中心になりました」と話します。
客層にも変化が見られます。開業当初は30〜40代の男性が中心でしたが、最近では女性客や20代の若い層も増えているそうです。また、以前は「とにかく珍しいもの、インパクトのあるもの」を求める客が多かったのに対し、最近は「バランスの良さ」や「飲みやすさ」を重視する傾向があるとのこと。
「一時期のような爆発的な盛り上がりはないですが、安定したファン層が形成されつつあります」と山田さんは分析します。
コロナ禍を経て見えてきたもの
コロナ禍は多くのクラフトビール専門店に打撃を与えました。しかし、その中で新たなビジネスモデルも生まれています。
例えば、テイクアウトやデリバリーの強化、オンライン飲み会の開催、サブスクリプションサービスの導入などです。「お店で飲む」という体験が制限される中、「自宅で楽しむクラフトビール」という新たな楽しみ方が広がりました。
また、コロナ禍で苦境に立たされたブルワリーを支援するために、クラウドファンディングで資金を集める動きも活発化しました。これにより、ブルワリーとファンとの絆が深まったケースも少なくありません。
「コロナ禍は大変でしたが、本当にクラフトビールを愛するコミュニティの強さを実感しました」と別の専門店オーナーは語ります。
クラフトビールの魅力は色あせたのか
ブームの熱が少し冷めたとしても、クラフトビール自体の魅力は決して色あせていません。むしろ、より洗練され、深みを増しているとも言えます。
個性的な味わいの価値
クラフトビールの最大の魅力は、その多様な味わいにあります。大手メーカーのビールが比較的均質な味を目指すのに対し、クラフトビールは個性的な味わいを追求します。
例えば、フルーティーな香りが特徴の「IPA」、コーヒーやチョコレートのような風味を持つ「スタウト」、バナナのような香りがする「ヴァイツェン」など、様々なスタイルがあります。また、同じスタイルでも、ブルワリーによって全く異なる味わいになるのも魅力です。
この「多様性」と「個性」は、大量生産品には真似できない価値であり、クラフトビールの本質的な魅力と言えるでしょう。
地域性を活かした醸造の取り組み
日本のクラフトビールの特徴として、地域の特産品を活用した醸造が盛んになっています。例えば、和歌山の梅を使ったフルーツビール、北海道の昆布を使ったスタウト、沖縄の黒糖を使ったエールなど、地域色豊かなビールが各地で生まれています。
これは単なる「珍しさ」だけでなく、地域の食文化や農業との連携、地域活性化といった側面も持っています。地元の農産物を使うことで、農家との新たな関係が生まれたり、観光資源として活用されたりするケースも増えています。
「地域のストーリーを味わう」という体験は、クラフトビールならではの価値であり、これからも発展していく可能性を秘めています。
海外との比較から見る日本の立ち位置
クラフトビール文化は世界各地で発展していますが、国や地域によってその状況は異なります。海外の事例と比較することで、日本のクラフトビール文化の特徴や今後の可能性が見えてきます。
アメリカのクラフトビール事情
クラフトビール文化の先進国であるアメリカでは、1980年代から徐々に発展し、現在では全ビール市場の約13%をクラフトビールが占めています。ブルワリーの数も8,000を超え、多くの地域で地元のクラフトビールが日常的に飲まれています。
アメリカのクラフトビール文化の特徴は、「コミュニティとの結びつき」の強さです。多くのブルワリーがタップルーム(醸造所に併設された飲食スペース)を持ち、地域の人々が集まる場所になっています。また、地域のイベントや慈善活動に積極的に参加するブルワリーも多く、単なる「ビール製造業」を超えた存在になっています。
日本と比較すると、アメリカのクラフトビール文化はより「日常的」で「地域に根ざした」ものになっていると言えるでしょう。
ヨーロッパの伝統とクラフトの融合
ビール大国として知られるドイツ、ベルギー、チェコなどのヨーロッパ諸国では、伝統的なビール文化とクラフトビールの新しい波が融合しています。
例えばドイツでは、何世紀にもわたって守られてきた「ビール純粋令」という伝統がありますが、近年はその枠を超えた実験的なビールを造るブルワリーも増えています。ベルギーでも、修道院ビールのような伝統的なスタイルと、新しいクラフトビールの手法を組み合わせた商品が生まれています。
ヨーロッパのクラフトビール文化の特徴は、「伝統と革新のバランス」にあります。長い歴史に裏打ちされた技術や文化を尊重しながらも、新しい要素を取り入れて進化を続けています。
日本のクラフトビール文化も、日本酒や焼酎といった伝統的な酒文化との融合が進みつつあり、ヨーロッパに近い発展を遂げる可能性があります。
これからのクラフトビールの楽しみ方
クラフトビールの楽しみ方も、時代とともに変化しています。従来の「バーで飲む」というスタイルだけでなく、様々な楽しみ方が広がっています。
自宅で楽しむ新しい提案
コロナ禍を経て、「自宅でクラフトビールを楽しむ」というスタイルが定着しつつあります。それに伴い、自宅での楽しみ方を充実させるサービスや商品も増えています。
例えば、定期的にセレクトされたクラフトビールが届くサブスクリプションサービスは、自宅にいながら様々なビールを試せると人気です。また、クラフトビール専用のグラスや、適切な温度で保存するための冷蔵庫など、関連グッズも充実してきました。
さらに、自宅で簡単にビールを醸造できる「家庭用ビール醸造キット」も注目されています。自分好みの味を追求したり、友人と共同で醸造したりと、新たな楽しみ方が広がっています。
| サービス・商品 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|
| ビールサブスクリプション | 毎月厳選されたビールが届く | 3,000〜6,000円/月 |
| 家庭用醸造キット | 自宅で手軽にビール作りが体験できる | 10,000〜30,000円 |
| 専用グラス | ビールの種類に合わせたグラス | 1,000〜3,000円 |
ペアリングの可能性を広げる
クラフトビールと食事を組み合わせる「ペアリング」も、新たな楽しみ方として注目されています。ビールの種類によって相性の良い料理が異なるため、様々な組み合わせを試すことで、新たな味わいの発見があります。
例えば、柑橘系の香りが特徴的なIPAは、スパイシーなエスニック料理と好相性です。コクのあるスタウトは、チョコレートデザートやブルーチーズとの組み合わせが楽しめます。フルーティーなベルジャンエールは、フルーツを使ったデザートと合わせると、その香りが引き立ちます。
最近では、クラフトビールとチーズ、クラフトビールとチョコレートなど、特定の食材とのペアリングを楽しむイベントも増えています。また、料理レシピにクラフトビールを使用する「ビアクッキング」も人気です。
クラフトビールを「料理と共に楽しむ文化」として捉えることで、その可能性はさらに広がっていくでしょう。
クラフトビールは「終わり」ではなく「変化」している
クラフトビールブームは終わったのでしょうか? 答えは「終わったのではなく、変化している」と言えるでしょう。一時的な流行から、より持続可能な文化へと変化しているのです。
ニッチからメインストリームへの移行
クラフトビールは、かつては「マニア向けの特別なもの」というポジションでした。しかし現在は、より広い層に受け入れられる「メインストリーム」へと移行しつつあります。
大手スーパーやコンビニでクラフトビールが販売されるようになり、居酒屋チェーンでもクラフトビールを提供する店が増えています。また、価格帯も少しずつ下がり、より手に取りやすくなっています。
この変化は「ブームの終焉」ではなく、「文化の定着」と捉えるべきでしょう。一部の熱狂的なファンだけでなく、より多くの人が日常的にクラフトビールを楽しむようになっているのです。
持続可能な文化としての定着
クラフトビール文化が持続可能なものになるためには、単なる「珍しさ」や「トレンド」を超えた価値が必要です。そして、その価値は着実に形成されつつあります。
例えば、地域の特産品を活用したビール造りは、地域経済との連携を生み出しています。また、環境に配慮した製法や包装を採用するブルワリーも増え、サステナビリティの観点からも評価されています。
さらに、クラフトビールを通じたコミュニティ形成も進んでいます。ブルワリーツアーやビール祭りなどのイベントは、単にビールを飲む場ではなく、人々が交流し、文化を共有する場になっています。
これらの動きは、クラフトビールが一過性のブームではなく、日本の飲食文化の一部として定着しつつあることを示しています。
まとめ
クラフトビールのブームは終わったのではなく、新たなステージに移行したと言えるでしょう。爆発的な成長期を経て、現在は成熟期に入り、より持続可能な形で発展しています。大手メーカーの参入や消費者嗜好の多様化など、環境は変化していますが、クラフトビールの本質的な魅力は色あせていません。むしろ、地域性を活かした取り組みや新しい楽しみ方の提案など、さらに深みを増しています。これからもクラフトビールは、日本の飲食文化の一部として、静かに、しかし確実に進化を続けていくことでしょう。
おすすめのクラフトビールサブスクはこちら!